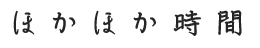
「お母さんが『今日は晩御飯を作りたくない!』って時に出てくる料理がこの『トマたま』。週に一回くらい食べていたぼくの家庭の味だよ。」
少し照れながらそう言うと、とても二人では食べきれない量のトマたまをちゃぶ台の真ん中に置いた。
社会人一年目。
横浜で働くこととなったぼくは、会社が保有する寮に入り、同期と共に一つ屋根の下で生活することになった。
朝起きてから寝るまでずっと誰かと一緒にいる生活(場合によっては寝る時も…。)は、ぼくにとっては刺激的でとても楽しかった。
同期で年齢が近いこともあり、話すことが尽きなかったぼくらは(ぼくは)、毎晩誰かの部屋に潜り込み、食卓を囲みあれやこれやと話した。
と言っても寮にありがちな食堂等も無かったため、その日集まる部屋の「家主」がご飯をもてなすというシステムで、学生時代からご飯を作ってもてなすことが好きだったぼくは、率先してみんなを呼んでいた。
いつものように小さなちゃぶ台をみんなで囲み、ご飯を食べていたそんなある日のこと。
隣にいたウェイクンという中国人の彼に出生について聞いたところ「ぼくは上海生まれだよ」という答えが返ってきた。
「え?上海??あんな大都市に実家があるの?どんな家?どんな生活??」
ぼくの妄想は止まらなかった。
上海といえば数回行ったことがあるが、近代的な街並みと人や車の多さに面食らった。
見たこともない電気自動車が走り、現代アートのような形をしたビルが空を突き刺している。ITが発達し、路地裏の屋台まで電子マネー対応。まるで未来へタイムリープしたような錯覚を覚えた。
それがぼくにとっての上海であるため、ウェイクンの話に興味が湧かないはずがない。
どんな生活をしているか。どこで買い物をするのか。何を食べているのか…。
矢継ぎ早に質問するぼくを見かねて彼が「じゃあ、明日の晩御飯はぼくが振る舞うよ!とっておきの家庭料理があるんだ!」
食い気味に返事をしたぼくは、さらに妄想を膨らませた。
北京ダック。いや上海だから上海ガニだろうか。いや飲茶や天津。はたまたふかふれスープ...。
うん、中華料理って宝石箱だ。
そして翌日、ドンと出てきたのがこの「トマたま」
イメージしていた中華とは違い、イタリアンのような佇まい。
一瞬「あれ?」と戸惑ったぼくを察知したウェイクンが「まぁ食べてみてよ!」と自信たっぷりに進めてくる。
ぼくはれんげでそれをすくい、口に入れた。
口に入れた瞬間、卵のとろみが口の中を覆う。でもいつもの卵とじとは何かが違う。卵が水分をしっかり含んでいてツルツルと食べられる。食感もプルプルで食べ応えもある。
直後に鼻先をくすぐる「ごま油」の香ばしさが、卵の食べ応えに一躍勝っているのだろう。
と思いきや、プチっプチっと弾ける酸味と甘味で後腐れない一口に仕上げてくれる。
「もう一口、もう一口」と我が食欲へのお膳立てを忘れない。
次はご飯に乗せて食べてみる。
気持ちいいくらい卵の水分がご飯に浸透し、みるみる金色がかったお米が完成する。
それを口にしてしまったらもう戻れない。
さっきまで「もう一口」だったのに、気づいたら「もう一杯」になっていた。
そうだ、このご飯が止まらない濃厚な味つけ。それでいてあと味スッキリで食べ疲れしないこの不思議な感覚。
この感覚こそ、まさしく中華料理だ。
やはり中華料理は宝石箱だ。
「おいしい!おいしい!!」
と言いながら山盛りのご飯とトマたまをかき込むぼくを見て、ウェイクンは嬉しそうに「トマたまが上海で一番美味しい料理だよ!」と言う。
ぼくはなんだか上海がずっと身近な街に思えた。
この後ウェイクンに詳しくレシピを教わり、今ではすっかり越野家の定番メニューである。
奥さんにぼくの料理で何が好きかと聞くと迷いもなく「トマたま!」と言ってくれるほど、気に入ってるようだ。
トマたまを食べた時の奥さんの笑顔も、さながら宝石箱のようだ。
ありがとう、トマたま。